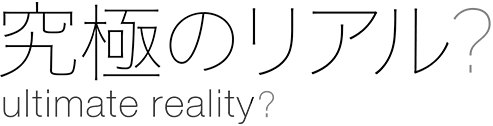| 2025/11/17 |
 |
2320 10年前のミラーレスα7sと60年前のオールドレンズ、ニッコールHオート50mmF2.0のセットがスナップシューターとして使えるか試してみた。絞りはレンズのリングで設定し、ISO自動を選ぶ。ライブビューで各種設定を反映させない表示を選ぶと開放測光と同等の明るさでピント調整ができる。フォーカスピーキングで老眼のサポートも万全(笑)ほとんど自動カメラと変わらない操作感!様々な光源で撮影したが ISO:6400までまったく問題なかった。カラーコーティングがなかった時代のレンズなので、やや古風な色合いになる。No.2315-2320 |