| |
下のbackボタンで過去へ進みます。 幻聴日記第1期 INDEX はこちらから photo and Text: machinist |
|
063 音の彼岸 その4 一本の伝送路 | | 正しく収められたステレオ録音(けして多くはないが)は、相当の精度で空間情報を記録している。同じ意味で、モノラル録音もフォルムとそれを取り巻くスペースを一本の伝送路に託しつつ、豊かな音場を刻み込んでいる。チャンネル間の干渉がない分、ストレスの発生する度合いも少ない。逆にステレオ録音で、空間情報をなくしているケースが多いのは、テクノロジーの皮肉か。前回(062)あげたレコードは、それぞれ1956・57年制作のモノラル録音。ステレオの必要をまったく感じさせないし、モノラルでなければ伝えられない世界なのかもしれない。 そういえば、コンパクトディスクが発表になった際、モノラル音源は倍時間収録できると伝えられたけれど、あれはどうなったんだろう。 (PENTAX*istD SIGMA 18-50mm/f3.5-5.6DC) 空の写真が続きすぎたので、次回はワンコ2連発です。 |
| 2004/05/11 |
|
062 音の彼岸 その3 無形のフォルム | | 音楽の美の価値は、無形であるということに尽きるのではないか。日頃、カタチに囚われる仕事に勤しんでいるせいか、形のないものが持つ放射力に強い憧れがある。といいつつ、優れた音楽には厳然と備えられたフォルムが存在すると思っている。たとえばアート・ペッパー「modern art」、あるいはセロニアス・モンク「himself」。時空を紡いだ先にある、みえないフォルムに圧倒されるばかりだ。「抽象美」とは、このことなのかな。(つづく) (PENTAX*istD FA ZOOM 28-105mm F4.0-5.6IF) |
| 2004/05/10 |
|
061 演歌、もう古典芸能でいいではないか。 | | きのう、ネタが尽きそうって書いたら「大変なんだねえ、でも続けてくれろ」というありがたい感想をたくさん戴いた。過去ログhtml化はアッという間に終わったので(画面右上から入れます)日記を続けます(笑)。 ジャズもクラシックも聴くけど、演歌だけは勘弁という人は多い。類型的な旋律と手垢にまみれた、そのくせあり得ないようなシチュエーションを歌っているのだからヘンだよね(笑)。ちかごろの演歌、とくに歌詞は悲惨な状況だ。長山洋子の「じょんから女節」はいい曲調だし、唄い込みも見事なもんだけど、最後が「♪あなたが欲しい〜」じゃーそれで終わり、気持ちが広がらない。あらたに演歌をつくる必然性って、いち早く覚えて自慢したいカラオケマニアのほかに何があるんだろう。 電気吹き込みの始まった昭和3年から昭和の終わりまで、あるいは20世紀終了まで広げてもいいけれど、我々が聴いたり歌ったりするのに、十分な楽曲が残されている。これらの表現を極めるという行き方はこれからでも価値があると思う。例えば古賀政男の最高傑作「無法松の一生」。この唄に備わる包容力を十全に表現した例を聴いたことがない。 写真:解体寸前のコタニビル、かつて新宿で最大のレコードショップだった。(PENTAX*istD FA ZOOM 28-105mm F4.0-5.6IF) |
| 2004/05/08 |
|
060 代数と幾何、あるいは離散と連続。大橋力の世界観 | | 「音と文明------音の環境学ことはじめ」(岩波書店刊)は、音の分野に限定されない広大な洞察力に圧倒される。著者の大橋氏は、情報や生体、環境を横断する学際的な研究者で、あの芸能山城組の主宰者山城祥二氏でもあるのは御存知のとおり。600ページの本文は、音楽制作の現場体験をはじめとして、知覚・意識の生体学的論考から数学、物理、音楽の各テリトリーを縦横無人に駆けめぐる大橋ワールド。非言語←→言語、幾何(量)←→代数(数値)といったようなアナログ、デジタルの両翼から、記号化で失なわれるものの重要性をくり返し述べているのが興味深い。これは、お買い物ガイドのはるか先に位置するオーディオ評論でもある。 写真:工事中の都立新宿高校とDoCoMoアンテナビル(PENTAX*istD FA ZOOM 28-105mm F4.0-5.6IF) 60回を期に過去ログをHTML化しました。 |
| 2004/05/07 |

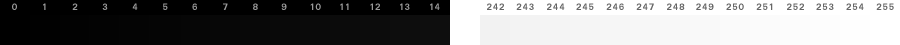
|
↑フルカラー(RGB各8bit)の精密グレースケールの両端を表示しています。すべてを正確に画き分けるモニターは存在しないと思います。
しかしながら「14」や「242」が識別できない場合はモニターレベルで顕著な黒潰れや白飛びが発生しています。ガンマユーティリティなどを使ってモニター調整することをお奨めします。 このページのすべての要素は製作者であるmachinistに著作権があります。複製使用等はご遠慮ください。 |







