| |
下のbackボタンで過去へ進みます。 幻聴日記第1期 INDEX はこちらから photo and Text: machinist |
|
616 聞き耳を立てる‥‥超偏見論 | | "聞き耳を立てる"も"目を凝らす"も同様だけれど、いずれも末端センサーをコントロールする"意識"により重心がかかるということを意味している。 ・ かの長岡鉄男氏は「スピーカーの支配力」という言い方をした。この力を備えないスピーカーは部屋の影響を受けやすいという意味だ。これは指向特性の問題が複雑に絡むが、本質は違うところにあると考えている。 ・ 「所詮、部屋だよ、オーディオは。」的なあきらめの言葉を聞くことがあるけれど、これは半分以上、誤りだと思う。スピーカーの特性に部屋の特性が重畳される様子はとても複雑で、例えばマイクロフォンは一元的な変化しか感知できないが、人間の耳と脳はもっと高級な処理をする。ぼくが音場測定に積極的でないのは、これが理由だけど、それは置いておいて(笑) 人間は部屋の特性を差し引いたスピーカーの音をある程度ではあるが把握できる。これは波形の成り立ちが異なるからで、先の"特性の重畳" で例えれば、黄と青が混じって緑になってしまうのではなく、独立した黄と青の細かい斑模様になるといえば、分かりやすい?もっと分かりにくいか(笑) ・ コンサートホールの二階席の最前列なら十分に検証できると思うが、演奏(楽器)にポイントを絞った聴き方、あるいはホールトーンに委ねる聴き方、いずれも可能だ。実際に先月、今月と実験してみたが明らかに異なるバランスの音を楽しむことが出来た。曖昧な数値を述べるのは躊躇うが、直接音2に対して間接音8が機械的測定結果だとすると、この比率を5:5くらいに無意識でアップして音楽を聴いていると思うし、さらに集中すれば7:3くらいまで高めることだって難しいことではないと思う。 ・ で、スピーカーの支配力の実体はなんだろう? たぶん立ち上がり特性の優れたものということではないか。生楽器がそうであるように。 |
| PENTAX*istD FA ZOOM 28-105mm F4.0-5.6IF 2006/01/17 |
|
615 完成版の試験アップ | | しばらく更新できない事情ができてしまった。"An ordinary spectacle"は、ほぼ完成しているので、このままアップすることにした。このページの画面下にあるリンクから入れます。 |
| EOS-1Ds MarkII EF50mm F1.8 2006/01/14 |
|
614 ラチチュード | | ラチチュードとは、正確には入出力のリニアリティのある部分を指すらしい。ただ、ぼくがこの言葉にいだくイメージは「寛容度」であって、撮影時の露出誤差をどのくらいまで救えるか、という意味だ。このふたつ、考えてみると矛盾しているよね(笑)。リニアリティを保てないから寛容性があると考えるのは、単なるへそ曲がりか? デジタルのリニアリティはフィルムと較べて優秀だけど、その外側はまったく救えないという意味で寛容性はなきに等しいのかどうか。個人的には十分に実用になっているし、器は大きすぎないほうがいいという思いもあるし・・・。 |
| EOS-1Ds MarkII EF50mm F1.8 2006/01/13 |
|
613 平林寺 | | 冬の陽が傾きかけるころ平林寺へ行った。禅寺の静謐な空気を撮りたいと思った。12点のシリーズで"An ordinary spectacle"に掲載する予定でいる。 |
| EOS-1Ds MarkII EF50mm F1.8 2006/01/09 |

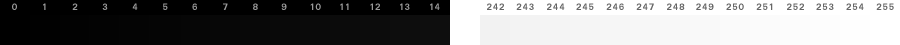
|
↑フルカラー(RGB各8bit)の精密グレースケールの両端を表示しています。すべてを正確に画き分けるモニターは存在しないと思います。
しかしながら「14」や「242」が識別できない場合はモニターレベルで顕著な黒潰れや白飛びが発生しています。ガンマユーティリティなどを使ってモニター調整することをお奨めします。 このページのすべての要素は製作者であるmachinistに著作権があります。複製使用等はご遠慮ください。 |







