| |
下のbackボタンで過去へ進みます。 幻聴日記第1期 INDEX はこちらから photo and Text: machinist |
|
620 EOS-D60 VII | | 30mm域でこの歪みのなさはどうだ(笑)もちろんノートリミングである。フルサイズではこうはいかない。 |
| EOS-D60 EF16-35mm 2006/02/08 |
|
619 EOS-D60 VIII | | 露出補正がサブダイヤルで常時行えるのは1Ds2と同じ。カスタム設定でISO感度が第一階層で設定できるのは超便利。1Ds2ではボタン二つ押したままダイヤル操作、両手ふさがって超不便だったので嬉しい。ただ、プレビューの拡大が3倍だけってところに時代を感じた。 |
| EOS-D60 EF16-35mm 2006/02/08 |
|
618 オールド・ニューカマー! | | EOS-1Ds2が仕事で稼働中はなんとなく落ち着かなくて、スナップに持ち出すのを躊躇してしまう。このところの日記を更新できなかった理由の半分はこれ。やっぱり*istDは置いておくべきだったと反省しつつ、こんなものを入手した。20Dからみればすでに二世代前のEOS-D60である。歴代EOS一眼DIGITALのなかではデザインが気に入っていた。お得意のデジック以前のモデルだし、AbobeRGBがないのもちょっと痛いけれど、色再現でのキヤノンらしからぬ不透明感は魅力だ。16-35mmF2.8が換算26-56mmで使えるのはスナップ用途にはかえって好都合だし、フルサイズでの周辺部の弱点が隠されるのもいい。*istDにシグマ18-50mmを付けていたときのように撮れればと思っている。 |
| EOS-1Ds MarkII EF100mmMacro 2006/02/07 |
|
617 隙間から世界を見る その1 | | ウエブの写真なんて200万画素で十分? 最終画像を900/600pxで使用するということは54万個の画素で成り立っているということだ。はたして1670万画素で記録する必然性があるのか。一般的なベイヤー配列の受光素子はR/G/B/Gというように3つの単色センサー(実際にはカラーフィルタで分色している)を市松状に配置しているので、正味のR/Bデータは表示画素数の1/4しか得られない。輝度信号もつかさどるG信号だけは表示画素数の1/2ということになる。それら全体を演算・補間して表示画素のデータを獲得している。 それでは、縮小リサイズにあたり、これ以上の高画素は意味がないという限界はどこにあるのだろう? Photoshopの高精度リサンプル形式である「バイキュービック法」では、元画像にローパスフィルタを掛けたうえでダウンサイジングを行う。(周囲16画素の濃度値から3次関数を用いて補間するそうだ・・・難しい!)要は近隣のピクセル情報を取り込み、補間の素材にするためだが、この原理から邪推すると、ひとつのピクセルの周囲一周分のデータ(3×3)くらいは縮小であっても反映するはずだ。ということは9倍である。900/600pxの最終画像のためには486万画素が臨界点ということになるかもしれない。まあ実際にはこの写真のような手ブレやレンズ性能の限界もあるから、そうシビアになる必要はないが、最近のデジタル伝送の液晶モニターは、非常に正確なピクセル表示をするので、印刷以上にシビアな面もある。ウエッブだからといって侮ると、それなりのものにしかならないということは大いにあり得る。 |
| EOS-1Ds MarkII EF16-35mm 2006/01/28 |

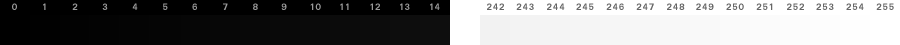
|
↑フルカラー(RGB各8bit)の精密グレースケールの両端を表示しています。すべてを正確に画き分けるモニターは存在しないと思います。
しかしながら「14」や「242」が識別できない場合はモニターレベルで顕著な黒潰れや白飛びが発生しています。ガンマユーティリティなどを使ってモニター調整することをお奨めします。 このページのすべての要素は製作者であるmachinistに著作権があります。複製使用等はご遠慮ください。 |







