| |
下のbackボタンで過去へ進みます。 幻聴日記第1期 INDEX はこちらから photo and Text: machinist |
|
657 | | 昨日の日曜日、レイオーディオの大型スピーカーをお使いの浦和N氏宅を訪問した。15年使い続けているというヴァーティカルツインモニターRM-8Vをドライブするのは定番パワーアンプJMF。オラクルのトランスポート、イルンゴオーディオのブルーイルミネーテッドDACとパッシブフェーダーというシンプルかつ盤石の構成。これだけの大型スピーカーがタイトでクイックな音楽表現をすることにちょっと驚いた。はじめに音楽があって時間をかけて装置をフィットさせる流儀がうれしい。氏のHPはこちら(音楽が鳴るのでPCのボリュームにご注意!)→http://www16.ocn.ne.jp/~narumiya/ そういえば、わが家のオリジナルスピーカーも来月で満10年。大きな音が出るという意味ではN氏邸のツインドライブに全然負けてない。ってそんなこと自慢にもならんか(笑) |
| CAFE DODOにて PENTAX *istDS FA31mm F1.8AL Limited 2006/03/20 |
|
656 | | 画像も音響も記録できるのは表層の変化でしかない。それらを手がかりに内部あるいは構造を知るのは人間の演算能力だ。この一元的なデータ列に画一的な処理、たとえば輪郭強調や特定帯域の強調のようなものを施すと、内在している立体情報を少なからず損なうのは写真もオーディオも同じだ。 |
| CAFE DODOにて PENTAX *istDS FA31mm F1.8AL Limited 2006/03/20 |
|
655 | | 表層とコアに境目は存在せず、すべてはシームレスに繋がっているわけだが、ある現象がより表面に近い部分で発生しているのかコアにふれあっているかは判断できると思う。デジタルもアナログも記録できるのは表面の変化値なわけで、このサーフェイスは立体の投影でもある。山の稜線は裏側の世界を幾分とはいえ表現しているはずだ。コアだから精神論というわけではないのだ。 |
| PENTAX *istDS FA31mm F1.8AL Limited 2006/03/20 |
|
654 | | 音のない音楽や文字のない文学はあり得ない。それぞれが固有の方策・手段を用いるから表現たり得ている。制約やフォーマットのないところでは、他者へ放射するようなチカラは発生しない。抵抗があることで電圧が生じるのと同じだ。しかし、音=音楽ではないし、文字がそのまま文学になる訳ではないだろう。表層を剥ぎ取った表現の「核」は、手段である音や文字の領域を使いながらもまったく別のところにある。 ・ オーディオ機器におけるテイストのとらえ方だが、わたくし的傾向(悪い癖?)で考察すると、どうも世間では表層の部分にポイントを置きすぎていると思うのだ。音楽のなかの何がどう伝わるかが最重要なのだから、いち個人が音楽に向かい合うのにテイストのバリエーションは必要なのかどうか・・・。あれは高校生のころか。オーディオへの興味が自分のなかでかなりのスペースを占めるようになって思ったことは、モンクとエバンスではオーディオに求めるものが異なるだろうということだった。もっとも、エバンスの底知れない闇を知った今では、そのようなステロタイプな考えは採らないけれど、表層とコアという分類を無意識にしてしまう傾向はいまでも続いている。本当は境目なんかなくてすべてはシームレスに繋がっているのだろうけれど。 |
| istDS FA31mm F1.8AL Limited 2006/03/14 |

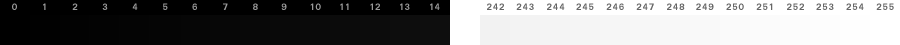
|
↑フルカラー(RGB各8bit)の精密グレースケールの両端を表示しています。すべてを正確に画き分けるモニターは存在しないと思います。
しかしながら「14」や「242」が識別できない場合はモニターレベルで顕著な黒潰れや白飛びが発生しています。ガンマユーティリティなどを使ってモニター調整することをお奨めします。 このページのすべての要素は製作者であるmachinistに著作権があります。複製使用等はご遠慮ください。 |







