| |
下のbackボタンで過去へ進みます。 幻聴日記第1期 INDEX はこちらから photo and Text: machinist |
|
227 「AUDIO & MUSIC」というサイトのいちコンテンツです。 | | この幻聴日記、ご覧になった方からときどき反響をいただく。なかには「いったい誰にむかって発信しているのか。マニアックな話題を相手かまわず振りまいて自慢でもしてるんか・・・」みたいな厳しい批判もある。「日記」と銘打った個人的内容をウエブで公にしているのだから、批判の対象になるのはじつは本望なわけで、もっとシビアな反応をいただけるなら一層ありがたい。とはいえ、このページは「AUDIO & MUSIC」というサイトのいちコンテンツであるという位置づけを変えるつもりはないので悪しからず。 写真は道でばったり出会った知人とドトールコーヒーでよもやま話が盛り上がったついでに、PENTAX*istD のマニュアル動作がいかに優れているかというデモンストレーションで撮ったワンショット。マニュアル露出、マニュアルフォーカスである。(PENTAX*istD SIGMA 18-50mm/f3.5-5.6DC) |
| 2004/12/17 |
|
226 温帯低気圧 | | 昨晩、NHK-BSでオン・エアーされた「わが麗しき恋物語 〜 クミコ ドラマティックコンサート」にたいそう感銘を受けた。先月おこなわれたオーチャード・ホールのリサイタルの模様をシンプルに構成したセンスとサウンドクオリティも際だって良かったけれど、なによりクミコさんの等身大で自然な雰囲気と歌詞に込められた「言霊」の輝きに、90分間、身じろぎもせずに聴き入ってしまった。 以前「もう森へなんか行かない」をCDで聴いたとき、マットで心地よい質感に好感をもったのだけど、すでにあのレベルをはるかに越えているのではないだろうか。歌のなかのドラマへ注ぐフォーカスや聴衆への放射力は、日本語で歌う女性ヴォーカリストとして故人を含め最高レベルに肉薄していると思った。彼女が持つ、とてつもないポテンシャルは、自身の全貌を見せる前段階を物語っていると感じる。これから10年20年の歳月をかけて大輪の花を咲かせるのではないか。 ・・・ふと、温帯低気圧のことを連想した。熱帯低気圧(台風)は海水温度が下がるエリアに入ると急速に衰えるけれど、あれは低温であっても衰えるすべを知らないばかりか、オホーツク海で巨大に発達したりする。このあいだ東京地区に観測史上最大の風速をもたらしたのも温帯低気圧だった。(PENTAX*istD FA ZOOM 28-105mm F4.0-5.6IF) |
| 2004/12/14 |
|
225 非接触 | | 土曜日に浦和まで出向いて、レーザーターンテーブルを体験してきた。このプレイヤーはアナログディスクの音溝にレーザービームを照射し、反射率の変化から溝の変動を測り、音楽信号を再構築するハイテクマシンであるが、すべてのプロセスをアナログで処理しているところがいっそう凄い。機械としての興味はもちろんのこと、持参した数十年前のSPディスクがどのように再生されるのかに大きな関心があった。 まず宮城道雄の「春の海」のオリジナル盤は非常に反りが激しく最大3ミリ程度上下するが、これを一度も途切れることなくトレースした。わが家では針圧を2割ほど増やしてようやく演奏できる代物だ。もうひとつのサボイ盤チャーリー・パーカーはコンディションの良いディスクではあるが、会場にいた全員が驚いたくらいの見事な再生音。耳障りなはずの摺動ノイズは空気の薄い膜を通したかのように「フワッ」っと軽い感じ。パーカーのビッグトーンも若き日のマイルスもライブネスを湛えた鮮明さで1937年の録音だなんてとうてい信じられない。 電気録音のSP盤に限れば、このレーザーターンテーブルは最高の仕掛けではないかと感じた。LPディスクはどうかというと、これはスタイラスで剔るほうが実体感で勝っているかもしれない。トレース時の塩化ビニルの変形やピックアップ系の共振などをディスク自体が見込んで作られていたのかどうか、これは断定はできないが・・・。(PENTAX*istD FA ZOOM 28-105mm F4.0-5.6IF) |
| 2004/12/14 |
|
224 モノーラル その3 | | 多元伝送系は「場」のサンプリングと言えなくもないから、人間のヴァーチャル感性は48CHくらいまでは対応できそうな気がする。その暁には、脳内処理はオーバーフローし、音楽の抽象性をつかみ取るセンサーは、きっとお留守になるんだろうなあ・・・。とはいえ音楽再生において「場」の再現は重要であると思う。音波の発生する在処は「場」の上にしか成り立たないから、曖昧な表現では虚ろな実体感の乏しい「音の雲のようなもの」になるか、あるいはスピーカーの振動板が楽器にすり替わるような「単純リアル」のどちらかになるだろう。非難を承知でいうと、いちばん正しい「場」を感じさせるのは、いまでも「モノーラル」ではないかと考えている。モノーラルはひとつの球体(半球体)として波面をひろげていくから。(PENTAX*istD FA ZOOM 28-105mm F4.0-5.6IF) |
| 2004/12/13 |

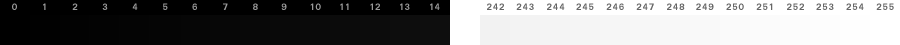
|
↑フルカラー(RGB各8bit)の精密グレースケールの両端を表示しています。すべてを正確に画き分けるモニターは存在しないと思います。
しかしながら「14」や「242」が識別できない場合はモニターレベルで顕著な黒潰れや白飛びが発生しています。ガンマユーティリティなどを使ってモニター調整することをお奨めします。 このページのすべての要素は製作者であるmachinistに著作権があります。複製使用等はご遠慮ください。 |







