| |
下のbackボタンで過去へ進みます。 幻聴日記第1期 INDEX はこちらから photo and Text: machinist |
|
588 | | キヤノンのサービス窓口でファームウエアのバージョンアップとセンサークリーニングをしてもらった。フィルムスキャンだって埃皆無ということはあり得ないから、センサーダストについて、あまり神経質になることはないと思う。たいていはブロワーで吹けばほとんど何処かへいってしまうし(笑)。そういえばPENTAX*istDのセンサーはゴミが付つきにくかった。 |
| EOS-1Ds MarkII EF50mm F1.8 2005/12/10 |
|
587 And more... | | 高校2年のときクラシックギターを2か月だけ習った。地元の名曲堂というレコード屋2階のヤマハギター教室。なぜ2か月かというとクラス担任が受験を控えてそんなもんやらせるんじゃないって、親に忠告したんだ。ったく大きなお世話だ。その教室は生徒が少なくてたいていは個人レッスンだった。習得レベルに応じてその場でアレンジして譜面を書いてくれた。田辺さんっていうのだけれど、いい先生だったなあ。 ・ Stratocaster1954(Fender Japan 40th Anniversary model) |
| Leica digilux1 2005/12/08 |
|
586 港が見える丘 WinterVersion | | ジャズギターでストリートデビューしようという計画は何年も前に頓挫した。すこしは素質があると思ったのだが、手が追いつかなかった(笑)。これを世間では才能がないと言うのだろう。いま密かに企んでいるのは演歌の弾き唄いだ。"無法松の一生"をオリジナルアレンジで完成させるのが老後の最大の楽しみ。問題は"唄"だなあ。 今日は年末スペシャルということでギター演奏を公開する。大好きな"港が見える丘"を師走の街のイルミネーションをイメージしてアレンジしてみた。いつもご大層な論陣張っているくせに、こんな拙いプレイを晒すか!と眉をひそめるアナタ。クリックしない自由もあるということでご容赦ご容赦・・・。 →http://www.vvvvv.net/audio/sound/minatogamieruoka.mp3 |
| EOS-1Ds MarkII EF70-300mmDO 2005/12/07 |
|
585 再び、音の在りかについて | | 先日の紀尾井ホールでの体験は、生演奏とオーディオ再生を考える意味でも大きな示唆を与えられた。その一つは、たとえアコースティックな楽器であっても、そのサウンドは演奏者自らが創り出すものだということ。もとより楽器とは不完全なものである。例えば三味線は駒(ブリッジ)の選定や、"さわり"量の加減など、音を変えるパラメータが非常に多い。 ※"さわり"についてはこちらのページを参照:http://www.vvvvv.net/audio/syami03.html ・ もう一つは、演奏と音が確固たるものとして生まれ出ても、空間に解き放たれた瞬間に、その音は極めて不確かな存在になるということだ。演奏者のステージ上の位置や床との接地状況、背後の音響条件、空間固有の特性、さらには聴取位置 etc...。これらの何かが変われば聴き取れるサウンドは異なる側面を示す。いったいどこに原音があるのか。普遍的な"原音"というものはこの世に存在しないのかも知れない。 ・ 演奏者自身がこころに描く原音イメージというものは一流の音楽家なら当然持っている。しかし、さまざまな理由で理想とは隔たった状況で演奏することは大いにあり得る。しかも、オーディオ再生の問題を考える場合、録音というプロセスに関わる人間が上記の理想イメージを共有しているとは限らないし、新たな価値(あるいは弊害)を付加される場合もある。再生では、聴き手がその音楽と演奏者に対してどのようなスタンスを取るのかが問題になるだろうし、よりアクティブにその音響(再生という意味の)に向う余地はあると思う。"原音"はそういった聴き手の意識の中により多く存在するのではないかと・・・。 |
| EOS-1Ds MarkII EF24-70mm 2005/12/05 |

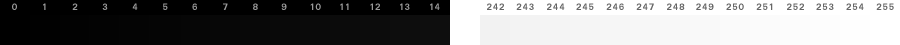
|
↑フルカラー(RGB各8bit)の精密グレースケールの両端を表示しています。すべてを正確に画き分けるモニターは存在しないと思います。
しかしながら「14」や「242」が識別できない場合はモニターレベルで顕著な黒潰れや白飛びが発生しています。ガンマユーティリティなどを使ってモニター調整することをお奨めします。 このページのすべての要素は製作者であるmachinistに著作権があります。複製使用等はご遠慮ください。 |







