| |
下のbackボタンで過去へ進みます。 幻聴日記第1期 INDEX はこちらから photo and Text: machinist |
|
771 URAWA II | | |
| ENTAX *istDS SIGMA17-70mmF2.8-4.5DC 2006/09/19 |
|
770 URAWA I | | |
| PENTAX *istDS SIGMA17-70mmF2.8-4.5DC 2006/09/19 |
|
769 諸々 | | 1シーン1ショットと決めている。なぜ、もっと違うアングルで撮らなかったのかと後悔することもある。フィルム時代のような"もったいない"という感覚とは違う。なんなのだろう? ・ 638で触れたPENTAX-Dが「K10D」という名称で来月発売される。SONY製10.2MpxCCDセンサーに4段分の手ぶれ補正、センサークリーニング装備、さらに防滴ボディと盤石の布陣!これで価格が10万円ちょっととは驚きだ。ニコンD80もキスデジXも蹴散らすことだろう。たぶん。 ・ キヤノンの画像処理エンジン「DIGIC III」が海外の公式サイトで発表された。ハイスピード、低雑音に加えて「顔検出機能」。なんとなく方向がわかると思ったら、一眼を通り越してコンパクトデジに一挙搭載らしい。やっぱり(笑) |
| PENTAX *istDS SIGMA17-70mmF2.8-4.5DC 2006/09/15 |
|
768 ニアレストネイバー法 | | これは法律の名前ではなく(笑)、画像のリサンプルアルゴリズムのいち手法である。前回767の写真は、いつも用いている「バイキュービック法」で処理している。それは元画像にローパスフィルタをかけ、近隣のピクセル情報を取り入れたうえでリサンプルし、あわせて若干のシャープネス処理を加えるという一連のプロセスのことを指す。 ・ 今回の「ニアレストネイバー法」はリサイズ後の新しい升目に合わせて元画像の特定部分の色を抽出するだけの仕組みだ。補完というプロセスは一切存在しない。さらにこの元画像ではRAW現像時のシャープネスを完全ゼロに設定している。シャープネスによる輪郭強調で階調が変化するのを嫌ったわけだ。(前回767の元画像は最低限のシャープネスが加わっている) ・ 写真のような自然画ではリサンプルに「ニアレストネイバー法」を使うことは、まずあり得ない。しかし、処理段階で新たな色を作り出さないメリットは当然あると考えている。もちろん写真としてどちらが優れるとかの話しではないし、水平・垂直線などは「ニアレストネイバー法」ではジャギーが目立つケースも出てくるだろう。実際、この写真ではステンレスプレートのヘアーラインがやや点線状になっている。 ・ 仕事場のモニターはCRTだけなので結論は出せないが、解像感は、こちらのほうが勝っているし、意外なことに階調再現性も気にならないとレベルだと思った。デジタル伝送の液晶画面ではどうか? ややデジタル臭を感じるかもしれない。・・・今晩、家の液晶で見て唖然として削除するかどうか・・・ |
| EOS-1Ds MarkII EF100mm Macro 2006/09/13 |

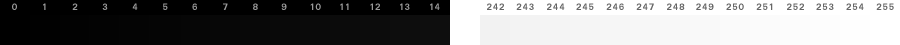
|
↑フルカラー(RGB各8bit)の精密グレースケールの両端を表示しています。すべてを正確に画き分けるモニターは存在しないと思います。
しかしながら「14」や「242」が識別できない場合はモニターレベルで顕著な黒潰れや白飛びが発生しています。ガンマユーティリティなどを使ってモニター調整することをお奨めします。 このページのすべての要素は製作者であるmachinistに著作権があります。複製使用等はご遠慮ください。 |







