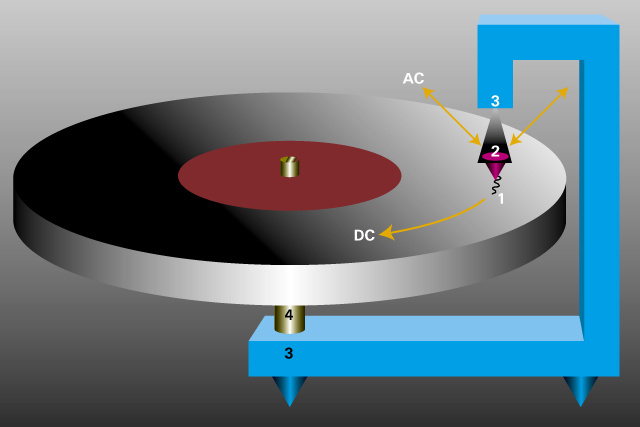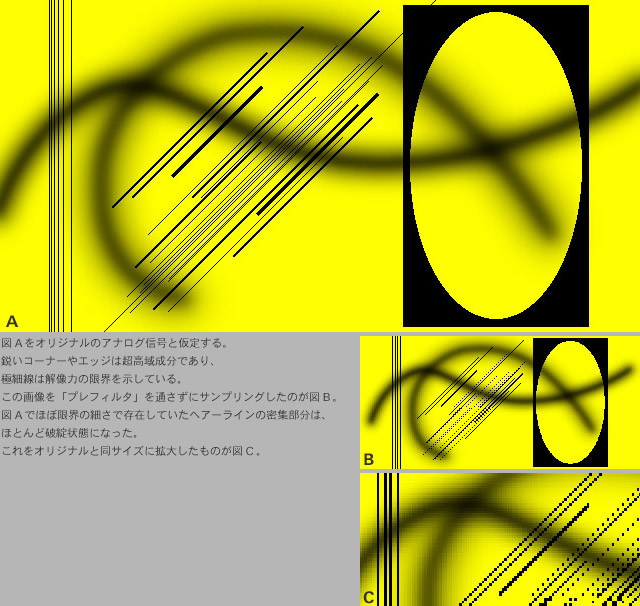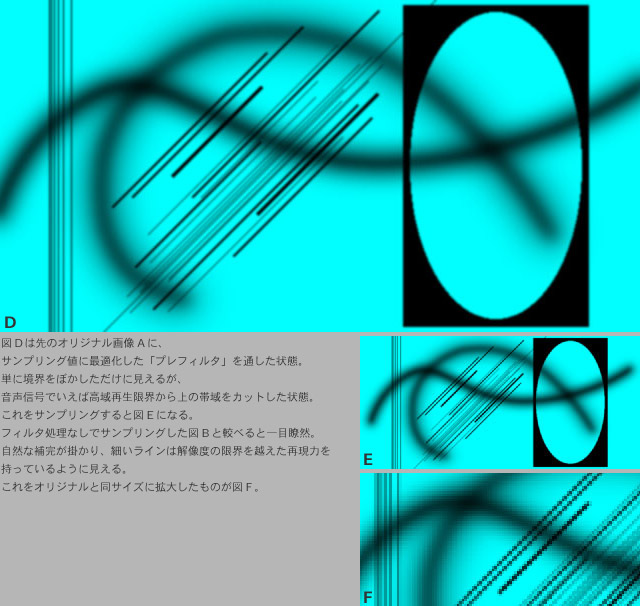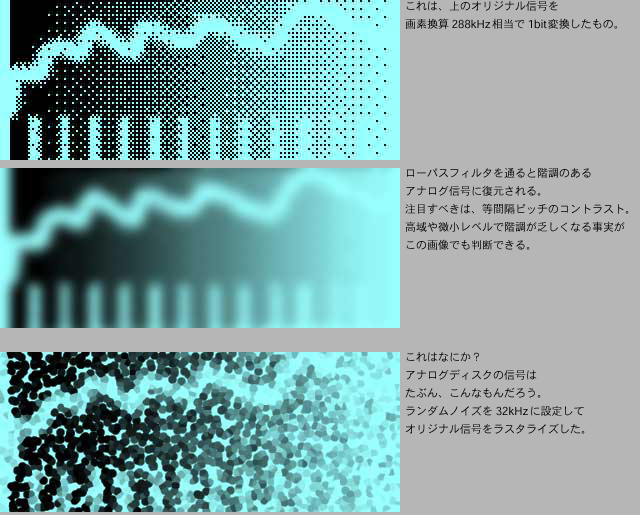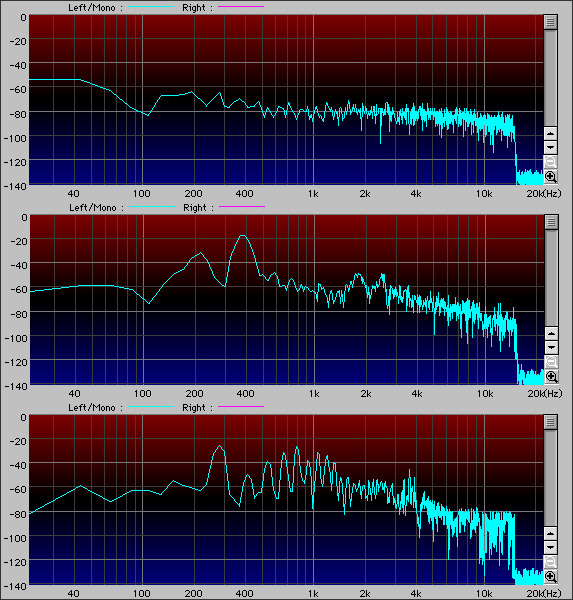◆音の彼岸 01, 02 ◆Voices 01, 02, 03 ◆Jazz and more 01, 02 ◆Thinking now 01, 02, 03
◆Sense of Audio 01, 02, 03 ◆My Favorite Cinema 01 ◆Cosmic on Bach 01 ◆MILANO1979 01 ◆三味線音楽 01
◆Personality 01, 02, 03, 04 ◆TOP PAGE→
幻聴日記 最新版はこちらから→
Photo & Text: m a c h i n i s t