| |
下のbackボタンで過去へ進みます。 幻聴日記第1期 INDEX はこちらから photo and Text: machinist |
|
042 フレームの存在 I 表現の次元 | | 032・・・構造を見せたいだけなのに輪郭を隠すことができないジレンマから、二次元平面による表現に軸足を移した、という話のつづき。 立体物は、われわれの生きている時空間と同一のキャンバスに置かれるので「表現」としての困難さを内在していると思う。三次元の外枠をつくることは可能でも、それは二次元のフレームが意味するものとは異なる。たいていは人形ケースのように、それさえもオブジェ化されてしまう。その点、無限に広がる平面表現というものは現実的ではない。フレームという暗黙の了解が二次元のカタチを成立させていると言えるし、送り手の表現意図を明確にする「仕掛け」でもあるわけだ。 ふと、オーディオの「フレーム」はどこにあるのだろうと思った。 (PENTAX*istD SIGMA 18-50mm/f3.5-5.6DC) |
| 2004/04/19 |
|
041 デジタルカメラ近未来図 | | ラチチュードの狭さは、写真表現という立場で考えると許せる気もする。でも、フィルムがCCDに換わっただけのデジカメって途中段階ではないかと思う。デジタル機器としてのインテリジェント性は著しくローレベルだ。AFもAEもフィルム時代から進化しているとは言えない。 近未来のデジカメは、人間の脳の情報収集の仕組みを取り入れるようになると思う。まず粗い情報を解析して、さらに必要な情報を取得する。このプロセスを繰り返すことで、求める精緻な情報にいたるわけだ。自然界の光の明暗も、事前情報をもとに複数回あるいは分割して取り込めば、銀鉛など遙かに及ばないダイナミックレンジを獲得できるのではないか。・・・某C社とか某N社は、とっくに着手しているんだろうなあ。しかし、そのあかつきには、写真で何を表現するかは難しい局面になっているだろう。制約の解釈はすなわち「表現」であると言えるから。 (Canon PowerShot A40) 一見キレイに見えるけど、もともとの階調はごく限られている。他の写真と較べるとデジカメっぽいよね。 |
| 2004/04/16 |
|
040 AEロックって使いにくいよね | | 長らく使っていたニコンF3は、手動絞りの電子シャッターだからAEとは言い難い面もあるけれど、このときの習性がいまだに抜けない。*istDでも絞り優先やマニュアルで使うことが多い。露出補正は画面内のここらアタリを基準にしよう、という意図でAEロックをかける。ところがこのロックボタンが操作しにくい位置にあるんだよね。もっともF3なんか、とんでもない位置にそれがあって実用性はゼロだったけれど。 で、シャッターボタンを微押しでAEロック、半押しでフォーカスロックってのは出来ないもんかねえ。そうすれば指をいっさい動かさないで、露出は地面の花びら、ピントは右の親父さんてのが出来る。人間の指もそのくらいは進化しているんじゃないかと(笑)。 (PENTAX*istD FA Macro 50mm F2.8) |
| 2004/04/16 |
|
039 ちあきなおみ 演じる歌 | | たとえば「矢切りの渡し」。永久の旅に漕ぎ出す男と女を、明確に唄い分ける。「クサイ」と言われればそうかもしれない。でもその作られた世界に聴き入ってしまう巧みさ。ほとんど浄瑠璃の世界だ。なおみさんは、いつも「その世界」の外側にいるんだね。どろどろの情念を唄っても、なにかクールな気配。男唄が上手いのはそのせい。テイチク時代の「男の郷愁」というアルバムはとくに好きだ。なかで「男の友情」と「居酒屋」は絶品ではないかなあ。 そして「朝日のあたる家」。戦後の焼け跡を舞台にした「ソング・デイズ」で唄ったし、去年リリースされたCD「ヴァーチャルコンサート」にも収録されている。極めつけはTBS-TVでオンエアーされた「すばらしき仲間2」でのスタジオライブ。これはもう壮絶としか言いようがない。仕草と歌唱が融合してパワーが8倍くらいになっている。まさに「演じる歌」の極北。 なかば引退してしまった、ちあきさんですが、もういちど生の声を聴きたい。演じない「素」の、なおみさんの内面の、こころの歌を・・・。 (PENTAX*istD FA Macro 50mm F2.8) |
| 2004/04/14 |

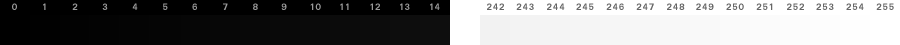
|
↑フルカラー(RGB各8bit)の精密グレースケールの両端を表示しています。すべてを正確に画き分けるモニターは存在しないと思います。
しかしながら「14」や「242」が識別できない場合はモニターレベルで顕著な黒潰れや白飛びが発生しています。ガンマユーティリティなどを使ってモニター調整することをお奨めします。 このページのすべての要素は製作者であるmachinistに著作権があります。複製使用等はご遠慮ください。 |







